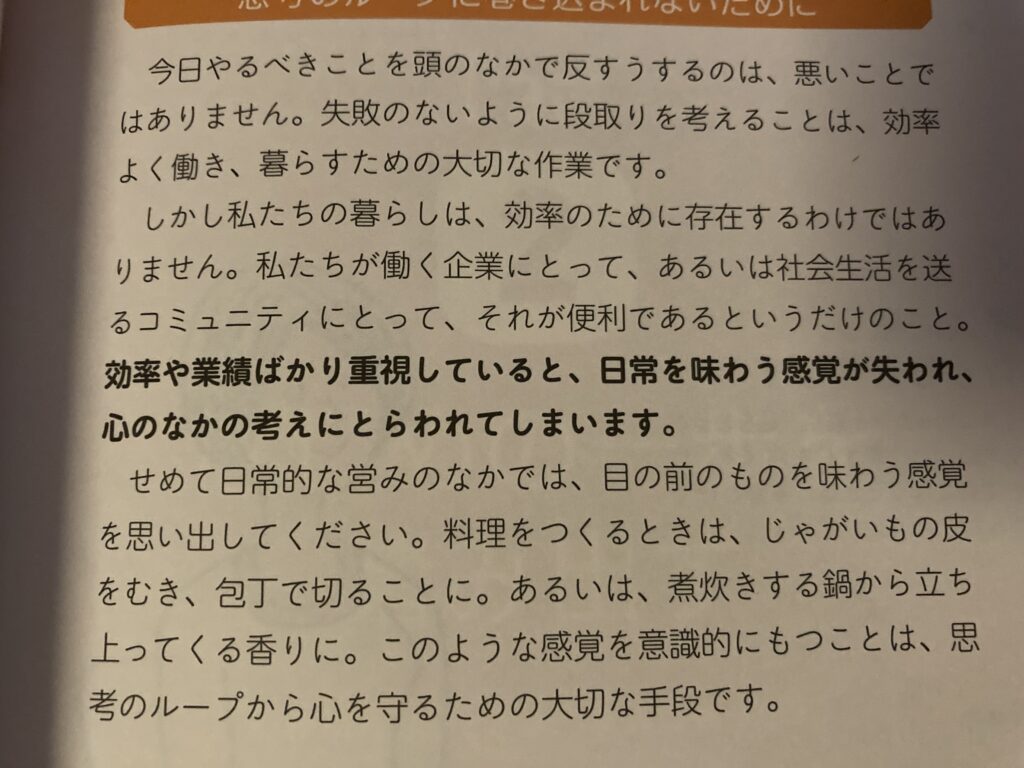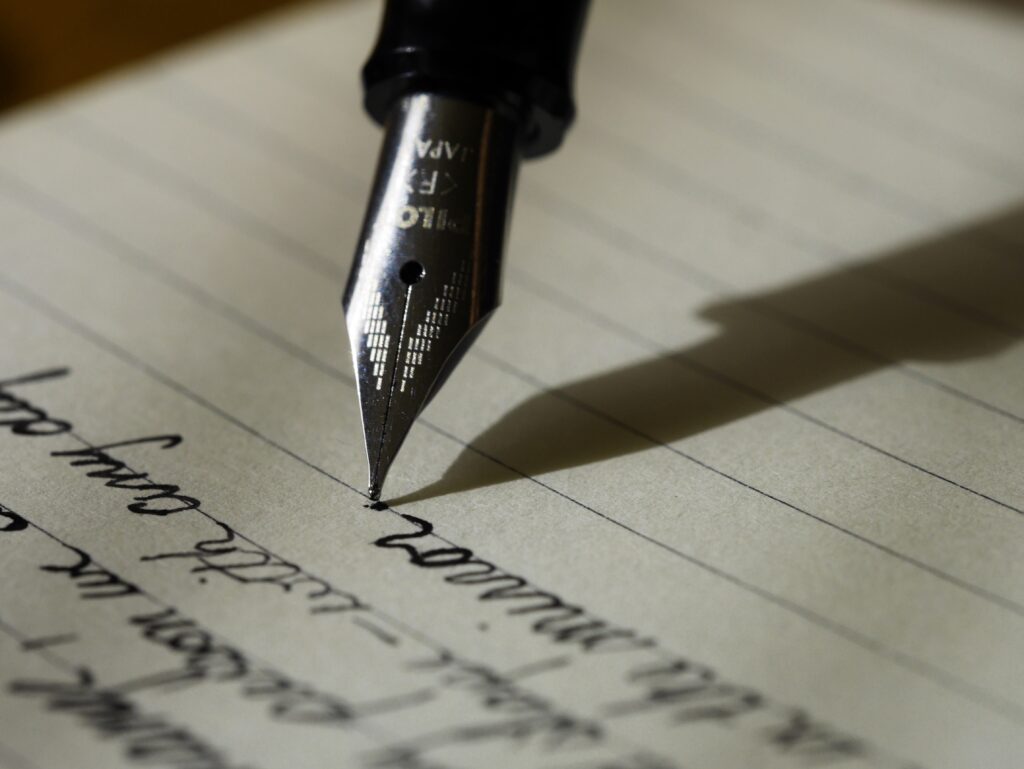今、漱石ほどの人材が、わざわざ日本語で小説なんぞを書こうとするであろうか。
-水村美苗「日本語が亡びるとき」
本記事は、水村美苗著「日本語が亡びるとき―英語の世紀の中で」の要約と考察です。
まず当書の内容を全体的にさらい、結論の確認まで行います。その後は、当書が書かれた2008年以降の状況の変化も踏まえ、日本語の運命について多少の考察を行います。(以後はである体で書きます)
著者について
著者は作家・水村美苗。12歳のとき、父親の仕事の都合でアメリカに移住したが、現地になじむことができず、自宅の日本文学全集を読んで過ごした。やがて作家として活動する傍ら、日本近代文学1をアメリカの大学で教えるようになる。その生い立ちから分かるように、日本近代文学を強固なバックボーンとしており、当書でも日本近代文学への強い憧憬を隠さない。
彼女は、自身にとっての日本近代文学を次のような情景で表現する。
「日本語で小説を書きたいと思うようになってから、あるイメージがぼんやりと形をとるようになった。それは、日本に帰れば、雄々しく天をつく木が何本もそびえたつ深い林があり、自分はその雄々しく天をつく木のどこかの根っこの方で、ひっそり小さく書いているというイメージである。」
重要な術語について
著者が独自の意味で用いている術語のうち、本記事で登場するものを紹介する。
まず、著者が提唱する三つの言語分類から。
・普遍語
→古くからある偉大な文明の言葉をはじめとした、知的、倫理的、美的に高みに達することができ、世界で広く学問の言葉として使われるような言語。かつては漢文やラテン語、現在は英語がこれに相当する。
・現地語
→人々が巷で話す言葉。基本は日常にしか用をなさない言語で、普遍語に対しては下位となる存在。美的に高みに達する可能性はあるが、知的、倫理的に高みに至ることはない。
・国語
→普遍語からの翻訳を通じ、現地語が普遍語と同じレベルの高みに到達できるようになったもの。近代国家の言葉として使われている。
以下はそれ以外の術語。
・日本語が亡びる
→文字通り日本語の最後の話者が消えることを指すのではなく、国語として高度な学問や言語芸術ができるほど進歩した日本語が、日常にしか用をなさない低級な言語(現地語)になり果てることを指す。
・二重言語者
→二つ以上の言語を読むことができる人。バイリンガルとは違った含みを持つ語で、叡智を求める人が二重言語者となり高度な知識にアクセスしてきたというような歴史的文脈で使われる。
・出版語
→著者ではなくベネディクト・アンダーソンの提唱した術語。印刷技術の普及に伴い書き言葉化した口語俗語で、方言が多数ある話し言葉とは違い数が限られている。国語のもとになる言語。
当書の要約
全七章だが一章、二章は序章的な内容なので、本論である三章以降を要約する。
当書読了済みの方は読み飛ばしても構わない。
三章:普遍語、国語の一般論
書き言葉は、話し言葉を書き表したものではなく、元来規範性をもった普遍語である。書き言葉は記録性、複製性をもつゆえに時空間的に広く行きわたる。書き言葉に参入する人間が増えれば叡智の蓄積が行われる。そして、それは一つの普遍語で行われるのが最も効率がよい。学問は本来普遍語で行われるものだ。
しかし、翻訳により国語が次々に誕生してから英語一強時代になるまでの間に、国語で学問を行った時代が存在した。その時代では学問の言葉と文学の言葉は分かれていき、前者は言語に依存しない翻訳可能な真理、後者はテキストに依存する翻訳不可能な真理を追求していった。そして、人間の本質的な問いを追求した文学の言葉は学問の言葉を超えるとさえ考えられた。これが「国語の祝祭」の時代である。この時代には、書き言葉の国語を規範として人々は自分の話す母語をも変化させていった。
四章:日本における国語の成立
日本語を国語として成立させた条件は三つある。
①それまでの日本語の書き言葉が成熟していたこと
②印刷資本主義が存在し、書物が流通していたこと
③日本が西欧列強の植民地にされなかったこと
①について。読書人の男は当然漢文を読み書きしていたが、和歌の地位向上により現地語の書き言葉であるひらがな文を男も読み書きするようになった。また源氏物語はじめ漢文との緊張感の中で書かれたひらがな文も存在し、日本語の書き言葉は十分な成熟に至った。
②について。江戸時代には資本主義が発達しており、教育により識字率も高かった。
③について。仮に植民地にされていれば日本語は現地語に衰退しただろう。実際には、欧米列強との衝突までに近代的軍隊を備えた国家に転身することができた。
近代化が喫緊に必要とされるなかで、読書人たちが漢文の素養を生かして欧州語を次々翻訳したことで、日本語は国語へと変身した。それにしたがい、日本近代文学を生み出すことが可能となった。
五章:日本における「国語の祝祭」
日本においては「国語の祝祭」は大いなるものとなった。非西洋語で学問をすることが困難であった2ゆえに、文学の言葉が学問の言葉を大きく超越したからである。その困難とは、日本語で学問をしても紹介者にしかなれないことと、学問用の翻訳日本語では日本の現実を真に理解できないことの二つ。実際、漱石は大学を離れ在野の人間として小説を書くことを選んだ。
優れた文学の第一条件は言葉そのものに向かうことだが、「西洋の衝撃」によりものを書く人は誰しもその必要に迫られ、日本近代文学の存在という奇跡を生んだ。
やがて時は経ち、国語はその起源を忘却され、自分たちの言葉と自然に認識されるようになる。すべての人が文学の読み手や書き手になれるような世の中になった一方で、日本語は亡びの道を辿りつつあった。
六章:英語一強の時代
「文学の終わり」が言われて久しいが、それを憂いることには根拠がある。科学の急速な進歩、文化商品の多様化、大衆消費社会の実現である。しかし、いかに文学の役割が狭まろうと本が消費財となろうと、読まれるべき言葉を読む人はいるので、広い意味での文学は終わらない。
本当の問題は、英語の世紀に入ったことである。英語は英米の国力だけでなく、非西洋人の英語への参入、そしてインターネットの登場で悠久の普遍語となり、学問は英語で行われるようになった。多くのテキストが英語で書かれ流通するようになるとき、叡智を求める人は英語でしか書かなくなるだろう。さらに叡智を求める人が国語を読みさえしなくなったとき、衰退の悪循環は始まる。英語以外の言語では文学が終わり、国語が現地語になりはてる可能性が出てきた。
学問を行う人はもはや大学を飛び出して日本語で小説を作ったりせず、英語世界に吸い込まれていくだろう。優れた文学を生む条件が崩れつつあるのだ。今、優れた文学は書かれているのかもしれないが、漫然と流通している文学は、かつての栄光を忘れさせるような低級なものだ。叡智を求める人は、社会についての文章を日本語で読むだろうが、文学だけは読まなくなってきている。文学は世界性から取り残されているのだ。
今、漱石ほどの人材が、わざわざ日本語で小説なんぞを書こうとするであろうか。それ以前に、果たして真剣に日本語を読もうとするであろうか。
七章:英語教育と日本語教育
英語の世紀では、まずは英語教育をいかにするか考えるべきである。方針は理論上三つ存在する。
①国語を英語とする
②国民全員がバイリンガルになることを目指す
③国民の一部がバイリンガルになることを目指す
①を日本は採用しないだろう。また、必要な人材は、外国人を道案内できる人材ではなく、世界に向って一人の日本人として優れた英語で意味のある発言ができる人材である。このような人材の育成には大変なコストがかかるため、③以外の選択肢はない。こうしなければ日本語は「亡びる」。
実際に何をするか。英語を多くの人ができればできるほど良いという思い込みが国民の中にあるが、それを否定し、まずは日本語ができるよう教育しなくてはならない。英語の基礎となる読解力のとっかかりだけすべての国民に与え、あとは豊富にある自主的に学ぶ環境に任せればよい。
次に、日本人が日本語を粗末に扱ってきた理由を考えよう。
一つ目は西洋語に相対した日本人が、日本語を下等なものと感じて自信を失ったこと。二つ目は、表音主義(書き言葉は話し言葉の音を表したものだという言語観)という誤った言語観によりさらに自信を失ったことだ。結局、表音主義的な現代かなづかいに改められてしまった。表音主義がいかに合理性を書いているかについては福田恆存3が述べている。表音主義は、すべての国民が書けることを目指しているようだが、読まれるべき言葉を読む国民を育てないことになる。それは文化の否定だ。三つ目は、日本列島の地理的条件により日本語が護られ、日本語が当たり前のものになっていたこと。だが、今やインターネットはじめ伝達技術の発展により日本語を隔て護るものがなくなってしまった。
最後に。
日本の国語教育はまず日本近代文学を読み継がせるのに主眼を置くべきである。
・出版語が規範性をもって流通することで、話し言葉が安定する。
日本の国語教育はまず日本近代文学を読み継がせるのに主眼を置くべきである。
・西洋の影響を受けた日本の現実を語るため、日本語の古層を掘り返し、あらゆる可能性を引き出した文学である。
日本の国語教育はまず日本近代文学を読み継がせるのに主眼を置くべきである。
・時代のもっとも気概も才能もある人たちが書いていた文学である。
この先、叡智を求める人が英語での読み書きに吸い込まれる運命は変えられない。
しかし、読むたびに「日本語に戻ってきたい」という思いに駆られる日本語であり続ける運命を、今ならまだ選び直すことができる。
以上。「日本語が亡びるとき」の論考は壮大ゆえ、ばさばさと内容をカットして要約せざるをえなかった。興味のある方は実際に本を手にとってほしい。
当書の結論:日本語は亡びるのか?
叡智を求める人が英語で読み書きするようになる潮流は変えられないので、日本近代文学を読み継がせる教育を行うことによって日本語を価値あるものに保ち続けない限り、日本語は亡びる。
考察:日本語はほんとうに亡びるのか?
現在、著者の提唱するような教育は行われていない。ではそのまま日本語は亡びるのか?ここからは、当書が書かれた2008年以後の状況変化も踏まえて日本語は亡びるのか考察してみたい。プラス点(亡びを避ける)、マイナス点(亡びを促進する)、その他に分けて考える。
プラス点1:ノンネイティブの参入
日本語を学習するノンネイティブの数は2008年当時と比べ増加しており、2021年には379万人の日本語学習者が世界に存在している4。多数のノンネイティブが日本語に参入し、また書くことで、日本語はこれまでになかった視点を獲得し、世界性をもつことが期待できる。この状況は、知的、倫理的、美的のいずれの観点でも日本語にプラスに寄与するだろう。
プラス点2:機械翻訳テクノロジーの発達
現在は2008年当時と比べ機械翻訳の品質が飛躍的に向上しており、大規模言語モデル(LLM)による高性能の機械翻訳が可能になっている。未だ最高度の翻訳は人間の手によっているものの、機械翻訳は十二分に役に立つもので、例えば二重言語者でなくとも英字新聞の機械翻訳から世界のニュースを簡単に知ることが可能となった。二重言語者以外の人間が英語の情報にアクセスすることが増え、その人が日本語で書くことで、世界と同時性を持ちかつ知的に優れた情報が流通する可能性が高くなる。
なお、作中の六章で言葉の修辞学的機能(反語、皮肉、隠喩など)を機械翻訳することは不可能と述べられていたが、ChatGPT5曰くAIには部分的には可能なのだそうだ。十分な文脈や表現の典型を用いるという条件付きだが訳せるのだという。これも当書の出版当時と比べテクノロジーが進歩した証だろう。
マイナス点1:言語体系そのものの美的凋落
まず、カタカナ語の氾濫について。言語は最新の現実に対応するために変化し、新たな語彙が生まれる。これ自体はあたりまえの現象だ。そのなかで外来の語彙が必要となることもしばしばあるが、そんなとき、近代日本では優れた漢訳が行われた。現在は、外来の語彙(基本的に英語)の多くはそのまま音写カタカナ語で入ってくる。そのように英語の語彙をほぼ生のまま日本語の体系のなかにねじ込むと、語意識の感覚を保ったままそれを使うのが難しくなる。例えば、overtourismは見るだけでover-tour-ismという語の構造が分かるが、を「オーバーツーリズム」と書けば、そのような情報は落とされる。ほとんどの人は、このようなカタカナ語の原語や構造、原語での用法など意識せず、日本語カタカナ語で使用される文脈から意味を読み取る。語意識の感覚など育たないのも当然だろう。しかも、「ナイーブ」のように英語と意味がズレているカタカナ語は語意識の感覚をもって使うことは不可能である。
次に、言語に潜む偽りについて。先ほどの「ナイーブ」もそうだが、誤用が当たり前のように使われ定着した言葉が無数に存在する。一部挙げれば、奨学金6、課金、すべからく、他力本願、確信犯、独壇場、ユニーク。このうち、すべからく7や確信犯を誤用と指摘する人はいるものの、奨学金や課金を誤用と指摘する人はもはや誰もいないだろう。誤用とは一時的ではかない認識でしかない。では誤用も定着してしまえば問題ないのかというとそうではなく、定着のたびに言語に偽りが潜み、言語体系に歪みを生じさせていく。そして、言語の美を少しづつ抉り取っていく。
最後に、現代仮名遣いと当用漢字制定の話。現代仮名遣いはそれになじむ現代人にはわかりやすいように見えるが、例えば当書の例を引用すると、「遠い」を「とほい」としなかったせいで、「とおい」なのか「とうい」なのかという問題が生じてしまう(そして特に必然性もなく「とおい」としている)。また、「きうり」を「きゅうり」としてせいで、「きゅうり」が「うり」の一種であるという語意識の感覚も鈍る。
当用漢字とは1946年に定められた、漢字を廃止しようという政治的な意図のもとに急いで作られた簡略体の漢字表である。漢字の伝統を理解した方法で行われた中国の簡体字と異なり、いわばテキトーな方法の簡略体で、旧漢字を体系的に理解している人から見ればとんでもない矛盾を含んでいるという。そして現在も常用漢字として簡略体が引き継がれている。カタカナ英語から逃れたところで簡略体や現代仮名遣いの歪みが待っている。このような様子を多和田葉子は「フェイクの闇市」8と表現した。現代仮名遣いも簡略体も多数の問題を持っており、語意識の感覚の鈍りに直結するがここでは深入りしない。
上で繰り返し述べてきた「語意識の感覚」について、当書ではこう書いてある。
「語意識の感覚が鈍った文章を読み書きするというのは、指先や足先へ神経がいかないまま舞を舞うようなものである。」
それは、とりもなおさず言語が美的に凋落することである。
マイナス点2:日本語の混乱と倫理的凋落
2008年の日本語は、2025年のそれと比べればはるか昔のものだろう。我々は2011年の大震災・原発事故を、2020年のパンデミックを経験してきた。この2つの大災害はそれまでとそれ以後の時代に断絶を生んだ。災害時の言葉は液状化し、SNSで様々な流言が飛ばされた。が、問題はそこではない。理不尽な現実に残酷にも「適応」した言葉が、メディアを通じて人口に膾炙したのである。2011年であれば被曝の現実に対して「ただちに影響はない」と言ってみたり、被曝量の基準を変更するような理不尽を言葉をもって通した。2020年であれば、病院にすら入れず自宅でうずくまる人々を指して「自宅療養」などと言ってみせた。そしてメディアが流通させたこれらの言葉を、様々な立場の発信者が、言葉を失うことなく再発信し続けた。
このような言葉のごまかしは、倫理的には致命的なintegrityの欠如にあたると思うが、それ以前に、「自宅療養」のようにそもそも嘘ではないかというのもある。私はこの世で一番邪悪な嘘は言葉の意味そのものを偽ることであると思う。そのような言葉が普及すれば、どんな正直者でもみな嘘つきになってしまう。ともかく、こういった言葉が重なり、言語に倫理的な歪みを生じさせる。
もう一つ、インターネットおよび短文式コミュニケーションの普及による言語環境の変化。そもそもインターネット日本語の言語空間はとにかく汚かった。倫理的には低劣もいいところで、ちょっと前の日本人は自分たちは治安がいい、民度がいいだのいいながらこの事実を無視してきた気がする。歴史的にはまず裏通りである匿名掲示板にて、煽りや中傷、嘲笑を基調とする汚染された言語空間が醸成され、舞台をSNSに移しても裏通りのノリを引き継いで汚染された言語で喧嘩している(相変わらず議論は成立しない)。そんなネットでは、通常の社会では存在すら許されないような激烈な侮蔑語(具体的には言わないが)がいくつか存在し、あまつさえSNS経由で影響を受けた子供たち9が悪口として…いや、時に悪いとすら思わずに使っているらしい。海外ではそれほどの汚染がみられないように思うが、言語の特性によるものなのか、かつての匿名掲示板の運営方針によるものなのかはわからない。
また、抽象的な表現より即物的で強い表現のほうが受ける、数字が取れるという言語空間が倫理的であることは難しい。
日本語の先行きは倫理的にも暗いだろう。
その他:AIについて
著者本人が最新のインタビューで述べるには10、小説はいずれAIでも書けるようになるし、人間に成りかわって思い出話を書けるでしょうけれど、生身の人間が生きて、年を取って、死んでいくという、その過程で経験したことに重みがある、という。なるほどAIは現実との摩擦を経験しない。マメが窒素固定の役割をもつように、体験した現実を文章化して固定することは人の役割だろう。AIが、人が主体的に書く権利を奪うならそれはマイナス点になるだろうが、現状その段階ではないようにも思う。
そのAIが、日本語の知的、美的、倫理的な面にどういった影響をもたらすか。結論、どの面に対してもあまり影響はないと思う。現在のAIは構造を学習して模倣するため、日本語そのものをエンハンスしてより高みに導くといったこともないし、あえて低劣な言葉の流通に寄与することもない。そもそも美や倫理は生身の人間にしか理解できないため、この領域においてAIが人間を超越することはまずない。
ただし、人工超知能まで出現してAIが知的に人間を超越するようになれば、日本語は大きな影響を受けるだろう。いや、そうなれば世界中の人類の存亡に関わる問題で、一つの言語がどうのと言っている場合ではなくなるだろう。
本記事の結論:日本語は結局亡びるのか?
英語の世紀が進むことは変えられないが、翻訳技術の発達やノンネイティブの参入により、知的には一定のレベルを保てる可能性がある。しかし、美的、倫理的な高みを担うことはできず、そのような面においては日本語は「亡びる」可能性が十分にある。
(終)
- 明治~昭和初期に書かれた、夏目漱石、森鴎外、福沢諭吉や二葉亭四迷をはじめとする、いわゆる「文豪」たちの文学。現代日本語の基礎を築いた。 ↩︎
- 伝統的な学問や自然科学は例外で、英文学のような西洋中心主義的学問がこれにあたる。 ↩︎
- 福田恆存「私の國語教室」(1960) ↩︎
- 海外の日本語教育についてhttps://www.mext.go.jp/content/20240722-mxt_-000037161_3-2.pdf ↩︎
- 一般に正確性を欠いているというが、餅は餅屋だと思いAIの限界はAI本人に聞くこととした。 ↩︎
- 奨学金の原語scholarshipは日本でいう貸与奨学金を意味しない。それは奨学金ではなく学生ローンだという ↩︎
- 「すべからく」をすべてという誤用は、残念なことに当書で使用されている。 ↩︎
- 多和田葉子「エクソフォニー」(2003) ↩︎
- 子供たちをとりまく言語環境については別の種本を使って書いてみたい。 ↩︎
- 中央公論 2025年3月号「日本語を亡ぼさないために」 ↩︎