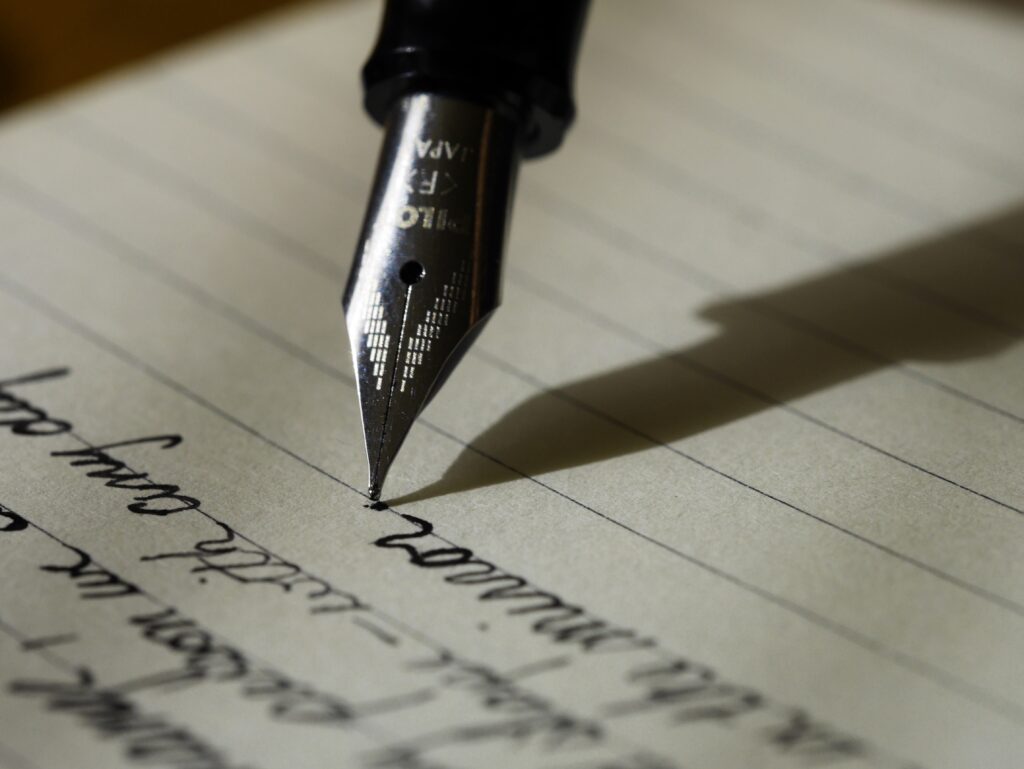
人がブログを書く目的は様々である。日記として使うため。趣味に特化して情報提供や交流を行うため。広告収入で稼ぐため。私の場合、日記に近いが、心の中に書きたいことがたくさんあるからそれを整理する、というのが目的である。
次に考えた。
ブログはWeb上に残存するものだから、他人にとって意義があることが望ましいと考えた。気にする必要はない、気楽にやればいいという人もいるだろう。その意見もありだと思う。だが、無意味な雑音を増やすだけにならないか?という不安が拭えずにいた。そこで、意義ある文章とはどんなものか?それは自分にとって実現可能か?を考えていった。
「日本語が亡びるとき」1では、後世に残って広まり、特に叡智を求める人に読まれるべき言葉を意味する、「読まれるべき言葉」という表現が使われている。
読まれるべき言葉とは第一には聖書をはじめとする聖典であって、その言葉を見た人はやがて自分でも書くようになる。書くといっても好き勝手するわけではなく、聖典の内容に対する解釈を書く。すぐれた解釈が残り新たな聖典とされる。このような聖典解釈学が、かつては唯一の学問であり、初めての「読まれるべき言葉の連鎖」であった。
今でいえば、「読まれるべき言葉の連鎖」に入ることは、古典や先行研究の系譜のなかに自身の著作が位置づけられることを意味する。
読まれるべき言葉の連鎖に入れるのは、一人前の論文と一部の本とごくわずかのインターネット上の文章だけである。遺憾ながら私自身にそのような能力はない。
読まれるべき言葉たらない言葉をいくら放っても、それは情報過多の地獄の火に油を注ぐだけである…諦めるべきだ…そうだろうか?
否、例えば、一流の情報以外にも必要な実用的情報が現にブログで書かれている。
少しでも価値のある文章を目指すことで、物を書くことは赦されるだろう。
「読書について」2では、思想(本)の価値は素材、または表現形式によって決まる、とある。何を考えたのかが重要なこともあれば、どのように考えたのかが重要なこともあるということだ。
前者の場合、独自性はものに依存するため著者がだれであっても重要性が保証される。後者の場合、よくある素材でもよいが、独自性は著者に依存するゆえに著者が優れていなくては優れた文章にならない。
読まれるべき言葉の連鎖に入るのはどちらでもありうる。
そうでないブログにおいて比較的価値のある文章を書きたいならば、卓越した著者を必要としない方法として、素材を生かす(例えば固有の体験や実用情報を書く)のがよいだろう。それは十分可能だ。
忘れてはならないのが、近年の大規模言語モデルをはじめとする生成AIの発展である。
厖大なデータを確率論的モデルに学習させることで、知っての通り、自然言語による質問や要求に自在に答える能力をもつ。
これにより、欲しい情報を求める質問があらかじめ決まっているなら「AIにきけばいい」ということになってしまった。ハルシネーションや誤情報の学習といった問題もあるが、このような趨勢を覆すようには思えない。過去の情報を引き出したりまとめあげる生き字引的な作業はAIに任せられるようになるだろう。
しかし、人の書く意義は依然としてある。
なぜならAIは生きていない。肉もなく、目や耳もない。
人の作り出したものを知っているだけで、ヒトそのものは知らない。
人にしかできないことをいくつかあげてみよう。
・この世界の現実を体験し、言葉にすること
・自身固有の経験をもって素材を編纂し、書くこと
・全く新たなアイデアを創造すること。確率論的モデルに悟りは開けない。
人がこの現実を生きているという事実こそが、AIとの差別化の最大のカギだと思う。人が固有の体験、素材を書き綴るようなブログなら問題ないだろう。
結論として、偉大なもの(読まれるべき言葉の連鎖に入れるもの)を書けないならば、固有の素材や体験、つまり自分らしいものを書くのが次善の策である、ということになるので、この方向で書いていきたい。
たとえ本に影響を受けていても、それは自分固有の経験とブレンドされ、独自の形や組み合わせで表出するだろう。
最後に、このブログは誰のためのブログか?
正直、まだ分からない。だが、考えることが好きな人なら、
何かを持って帰ってくれる、そういうものになるだろう。
さあ、ブログを始めよう。