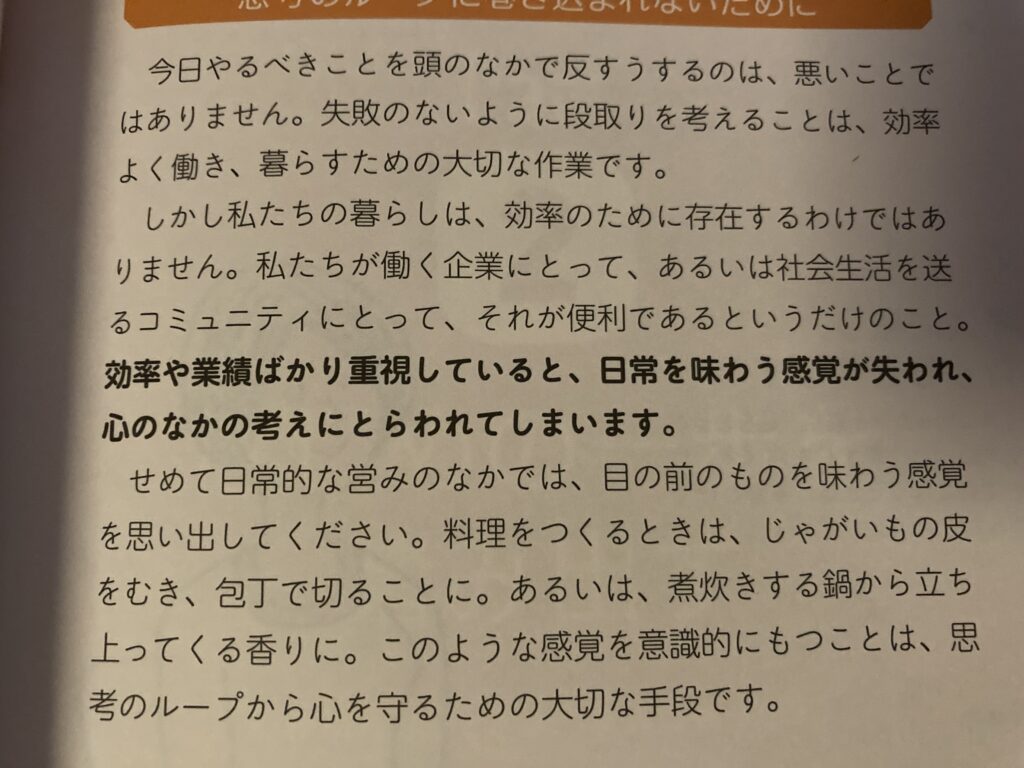
今の子供たちは大変だ。外国語やプログラミング教育ばかりか、多文化共生やジェンダーといったSDGs的な「常識」の理解なども必要とされる。
しかし、そのために教科や授業時間が新設されるでもなく、既存の教科の時間を減らして行われるがために、
基礎的な語彙や情緒、表現の能力が身につかず、与えられる内容を表面的に理解しようとするだけの砂上の楼閣状態になっている。
そんな状態で、情報が氾濫するジャングル -疫病や毒蜘蛛や蛇や殺人アリが跋扈する- に身をさらしている。
これが、「AIに負けない子供たち」を作ろうとする取り組みの現実のようである。
AIと勝負するとして、勝てる可能性はあるだろう。翻訳やプログラミングであれば、プロレベルの技術者はAIを超える成果を出すことができる。そもそも、我々の生きる現実を書くことは人間にしかできない。
しかし、AIと同じ土俵に立って負けない知的能力をつけるのは一般に難しい。分野によっては新幹線に負けない走力をつけるようなものだろう。人という生き物は未だ生物学的には野獣のままだが、機械には伸びしろがある。現在のようにAIとの勝ち負けを考えたり、成果・プロダクトの良し悪しに拘泥すれば、人類にはいずれ尊厳も居場所もなくなるだろう。「人間は必要ない」となるかもしれない。
人にとって第一の問題はどう幸福に生きるかであると思う。いかに一番交換価値の高いものを生み出すかを追求する生き方もあるが、それは一部でしかない。生きるというのは体験するということであり、幸福に生きることは体験を充実させることである。そして、それに主体性は欠かせないものだと思う。
人は泣きながら生まれ、ハイハイを覚え、二本足で立つ。ごっこ遊びを覚え、やがて授業に取り組み、社会性を身につける。働く。家事を覚える。
生きることが主体的な体験の積み重ねで、その充実が成果よりも本質的であると考えれば、AIは人類を打ち負かすものではなく、あくまで人類を補助するべきものでしかなくなる。(成果を目指すことも主要な自己実現の一つだが、それが交換価値である必要はない。)
人にとって理想的な生というのは、無限の点滴で自動的に栄養補給する生活ではなく、日々食事を味わったり作ったりする生活であろう(ほとんどの人にとっては)。
人が生活の中で主体的な体験を行う具体的な活動はいくつもある。
歩く、字を書く、料理する、絵を描く、楽器を演奏する、短歌を詠む、なんでもいい。充実していると思うなら仕事でもいい。
AIのようなテクノロジーは、人の役割を奪い主体性ある生活をするうえで脅威になるという面もあるが、逆に苦役から人を解放し、より自由に生活させることもできる。たとえば農業機械の発明は農民の時代を終わらせ多くの人々を解放した。より多くの人が自分のやりたいことをできるようになった。新たにこのような恩恵を受けられる可能性は残っている。
ここまで、主体性もってやりたいことやるのが人生の理想と書いてきた。
多くの人はそうだろうと思っているが、そうではない人もいるかもしれない。
ただし、人が芸術を生み出すにあたっては非常にクリティカルな問題で、新幹線で旅をしても奥の細道は生まれないように、主体的活動の省略が致命的な影響を与えると聞いたことがある。
私は人の手による文明が平和的に続いてほしいと思っている。そして、そのためにできることをしたい。
※第1段落の参考:石井光太「ルポ 誰が国語力を殺すのか」(2022)